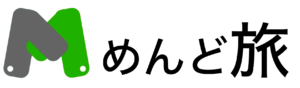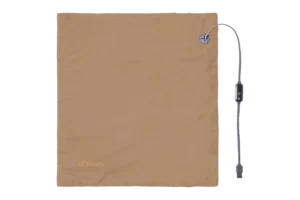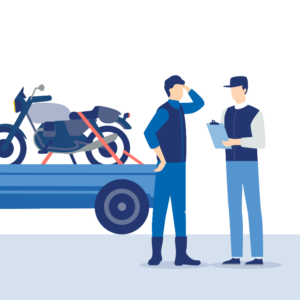津山城について
概要
津山盆地の中央部に位置し、城の東部を流れる吉井川支流の宮川及び丘陵の天然の断崖を防御線に取り入れている。
城の南部を流れる吉井川とその支流で西部に位置する藺田川(いだがわ)を外郭とし、その内側に城下町の主要部を形成している。
往時は外郭を含めて、広島城の76棟、姫路城61棟をしのぐ77棟の櫓が建ち並ぶ。
廃城令により天守・櫓などの建物が破却され、現在は遺構の石垣や建物の礎石が残った。
2002年(平成14年)から2006年(平成18年)までに再建された備中櫓と土塀がある。
津山城の位置
〒708-0022 岡山県津山市山下135
岡山県の北側に位置する。

景観
入場
入城は、鶴山公園
少し歩くが無料の駐車場があった。
料金は、数百円
桜の木がたくさん植えられていたので、春に訪れるのが良いかもしれない。
城にしては広い石段を登る。
ほんの一部のみ整備されていたが、9割以上はただの雑草の生えた城跡といった感じだったが、それでも、城があった当時を想像すると、日本有数の城だったことがわかる。

津山城の天守閣のあった石垣から備中櫓方面の津山の街を見下ろす。すばらしい!
鶴山公園(かくざんこうえん)
鶴山公園(かくざんこうえん)は、岡山県津山市にある歴史公園である。
明治の廃城令で民間に払い下げられていた津山城の中心部を当時の津山町が町有とし、1900年(明治33年)に鶴山公園として公開した。
津山城址鶴山公園ともいう。
古地名としては「つるやま」だが、城の通称、および公園名は「かくざん」である。
築城した森忠政とは
忠政は織田信長の家臣であった森可成の六男である。
可成は美濃金山城主で、忠政の生まれた元亀元年九月に近江宇佐山城で浅井・朝倉勢の攻撃を受けて討死した。
嫡男可隆はこの年四月に越前手筒山城の攻略で討死していたため次男の長可が森家を継いだ。
天正十年(1582)、長可は武田攻略の戦功により、信長から信濃川中島二十万石を与えられて海津城(松代城)に入った。
この直後、本能寺の変が勃発、長可は川中島を捨てて金山城に戻った。
この変で信長の小姓として近侍していた三男成利(蘭丸)、四男長隆(坊丸)、五男長氏(力丸)がともに本能寺に斃れた。