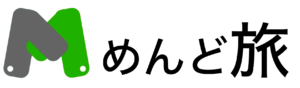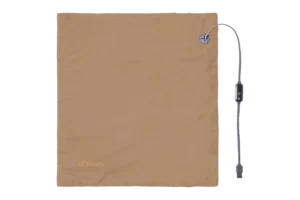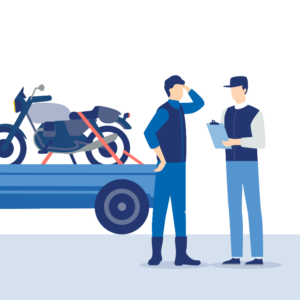禄剛崎(石川県珠洲市)
禄剛崎(ろっこうさき)は、能登半島の最先端で、ちょうど外浦と内浦との接点にあたるところです。この岬は「海から昇る朝日と、海に沈む夕陽」が同じ場所で見れることで有名です。
ほっと石川旅ねっと
禄剛埼灯台
禄剛埼に建つ灯台「禄剛埼灯台」(ろっこうさきとうだい)は、狼煙の灯台(のろしのとうだい)とも呼ばれ、明治時代に日本人の設計で造られた白亜の灯台です。
無人のため灯台内は見学不可ですが、年に数回一般公開があります。 1998年に「日本の灯台50選」に選ばれ、2009年には「近代化産業遺産」、2017年には「恋する灯台」にも認定されました。珠洲市観光サイト
位置
禄剛埼は、日本列島の中心、能登半島の先端に位置します。
〒927-1441 石川県珠洲市狼煙町イ51

禄剛崎の景色
道の駅 狼煙
禄剛崎灯台に行くには徒歩で行く必要があるので、
道の駅 狼煙の駐車場に停めて、案内看板に従って、道路(奥能登絶景海道)を横断します。
遊歩道は、綺麗に整備されていますが上り坂なので、運動不足の私には少々キツかったです。
禄剛埼灯台
禄剛埼灯台(ろっこうさきとうだい)は、能登半島の北東端に位置し、海面上46メートルの段丘上にあります。
明治時代に日本人の設計で能登半島の最突端、珠洲市の禄剛崎に建てられた石造の灯台。レンズを固定させ、遮蔽板を回転させることで灯火を点滅させる珍しい手法を用いた。石材を人力で崖下から運ぶ難工事の末に完成されたようです。
禄剛崎 能登半島
禄剛埼灯台は、純白で青い空によく似合います。とても110年余り前に建てられたとは思えませんでした。
禄剛埼灯台は現存する灯台では、能登半島で最も古い施設です。能登半島の最果ての地、禄剛埼周辺海域は古くから海難事故が数多く、北回り廻船の要衝を占める地として宝暦6年(1756年)に焚き火常夜灯設置の要望がなされ、背後の山伏山の一角に灯明台を築き、火皿に油を浸し、火を点じ海難の防止を図っていたと伝えられています。
明治16年、建設はすべて日本人技術者の手で建設されました。一世紀有余の風雪に耐えて、なお揺るぎない偉容を誇る石造りの灯台の石材は良材を求めて、遥か七尾湾の穴水町甲地区から搬出され、海路約60キロメートルを小船で運び、岬に索道を設け人力で現場へ引揚げるという難工事で完成まで約2年の月日を要し、建設費用は当時のお金で20,051円であったと言われています。
点灯以来110余年いまなお、最果ての地で灯し続けている禄剛埼灯台も昭和15年石油から電気に変わり、昭和38年機器の自動化が図られ無人化されました。
奥能登の最果ての地で明治の面影をとどめる美しい白亜の灯台で、「日本の灯台50選」に選ばれました。 また、平成21年2月、安全な船舶航行に貢献し我が国の海運業等を支えた灯台等建設の歩みを物語る近代化産業遺産群として認定されました。海上保安庁
千畳敷
灯台下の崖下には、「千畳敷」といわれている平らな海食棚が広がる。
干潮になると姿を現し満潮になると海中に没する。
一帯の地層は中期中新世(約1,500万年前)の海底で堆積した泥岩層で、硬質部と軟質部が交互に成層している。
岬自然歩道(禄剛崎をめぐるみち)
禄剛崎から椿展望台までまで 徒歩で片道 8km 2時間20分の自然歩道があるようです。
散歩が目的で天候が良くて、時間が許せば歩いてみるのも良いかもしれません。
往復5時間程度かかるので観光には適さないかもしれません。
現実的には、2絶景ポイントまで歩いて狼煙道の駅駐車場まで戻って、車やバイクで移動するのが良さそうですね。
3川浦園地
駐車場・トイレあり、
近くに川浦八幡神社
4シャク崎
近くに駐車場は存在しません。
能登半島の最北端の岬とされ、岬自然歩道を通って 勾配のある道を徒歩で向かうことができます。
9絶景ポイント
椿展望台からしばらく遊歩道を進むと断崖展望台があります。
10椿展望台
駐車場有
禄剛埼の地質
岬の北側の海岸線には、海岸と並行な泥岩の層による洗濯板のような岩石が見えました。
したがって、禄剛崎の地質も同様な、海成の泥岩と予想しました。
答えは、海成層 珪質泥岩でした。

肌色の部分は堆積岩
形成時代: 新生代 新第三紀 中新世 後期ランギアン期〜トートニアン期
岩石: 海成層 珪質泥岩
薄い緑の部分は堆積岩
形成時代: 新生代 第四紀 後期更新世前期
岩石: 段丘堆積物
です。いずれも堆積岩の岬のようです。
ランギアン期〜トートニアン期は、約1597万年〜1163万年前
海成層珪質泥岩は、太古の海の底で形成された特殊な種類の岩石です。
形成過程 プランクトンの死骸: 海中を漂う珪藻や放散虫といったプランクトンは、死んで海底に沈みます。これらのプランクトンの殻は、二酸化ケイ素(SiO₂)という物質でできており、非常に硬いのが特徴です。
堆積: 長い年月をかけて、これらのプランクトンの殻が海底に厚く堆積します。
圧縮と変成: 上から重なる堆積物の圧力と、地下の熱によって、堆積したプランクトンの殻が圧縮され、固い岩石へと変成します。この時、二酸化ケイ素が再結晶し、緻密で硬い珪質泥岩となります。Gemini
キャンプ場
鉢ヶ崎野営場
営業時間 7月中旬~8月31日
料金 テント1張り 1,200円 タープテント1張り 300円 ※貸テントなし
アクセス 奥能登転換バス「珠洲鉢ヶ崎」徒歩すぐ、すずバス狼煙飯田(海)ルート「鉢ヶ崎」徒歩すぐ
連絡先 鉢ヶ崎ケビン・鉢ヶ崎野営場管理棟
Tel 0768-82-4322
その他料金 水道清掃協力費として大人一人300円、小人一人100円が必要